
突然と共に生きること?
- kotatukz
- 8月24日
- 読了時間: 3分
大学のころ、生と死の倫理学という授業で、まとめの論文を書いた。『突然と共に生きていく』を題として、授業で学んだことや、そこから、私はどう自分の生と死と向き合っていけばいいのかを考えていた。
予測や予報が、正確(仮)にできてしまう世の中になって、突然が恐ろしく、そして受け入れられないものになっていないかをとても思っている。
分からないことは怖い…という感覚ももしかしたらこの情報の海によって身体が麻痺させられてるのかも。
わたしは未だに分からないことを楽しめない。全てのことに理由も言い訳も欲しい。(舞台芸術は分からなくても不安にはならないし怖くもならないけどね。)
先が見えないのは当たり前なのに、どうして毎日漠然と不安なんだろう。
どうして、ひねくれて、すぐに人や人の考えを受け入れられないんだろう。
NOと言える力をみにつけるのは、暴力に加担しそうになったときとかに役立つと思うから、忘れたくは無いし鍛えておきたい力だけど。
何から勉強したら、自分の生きている時代を知ることが出来るのか、悶々として、友だちも近くにいないから、チャットGPTにヒントをくださいって言ってみた。
そしたら、こうやって返ってきた。
1. 心理学・精神分析
人間の「不安」の根源を知ることは大きな武器になります。特にフロイトやユングは舞台芸術と親和性が高いです。
『フロイト入門』 (小此木啓吾)
『ユング心理学入門』 (河合隼雄)→ 夢や無意識の象徴を理解することは、観客の心に潜む不安を舞台に立ち上げる助けになります。
2. 哲学・実存主義
不安や孤独を「生の本質」として扱った哲学者たちの思想は、創作に厚みを与えます。
『死に至る病』 (キルケゴール)
『嘔吐』 (サルトル)
『カミュの不条理哲学』 (カミュ関連の入門書でも可)→ 人間が「なぜ不安と共に生きるのか」を考えることが、作品に普遍的な深みを与えます。
3. 社会学・文化人類学
不安は個人だけでなく社会や文化からも生まれます。
『リスク社会』 (ウルリッヒ・ベック)
『演劇とは何か』 (ブレヒト関連の文献)
文化人類学的なフィールドワークの本(例えば中沢新一の著作など)→ 「不安は社会が生むもの」という視点を持つと、舞台が「共同体の浄化の場」として意味を持ちます。
4. 宗教・神話学
「儀式性」を理解するには、宗教や神話は欠かせません。舞台の原点でもあります。
『神話の力』 (ジョーゼフ・キャンベル)
『演劇と儀礼』 (ヴィクター・ターナー)→ 神話や儀礼の構造を学ぶと、「舞台は現代の神話たり得る」という気づきにつながります。
よーし、ここからとりあえずお勉強してみて、私がどんな時代にいて、どうして舞台作家を目指しているのか、誰を観客にしたいのか、そして何を描きたいのかを探ろうと思う。

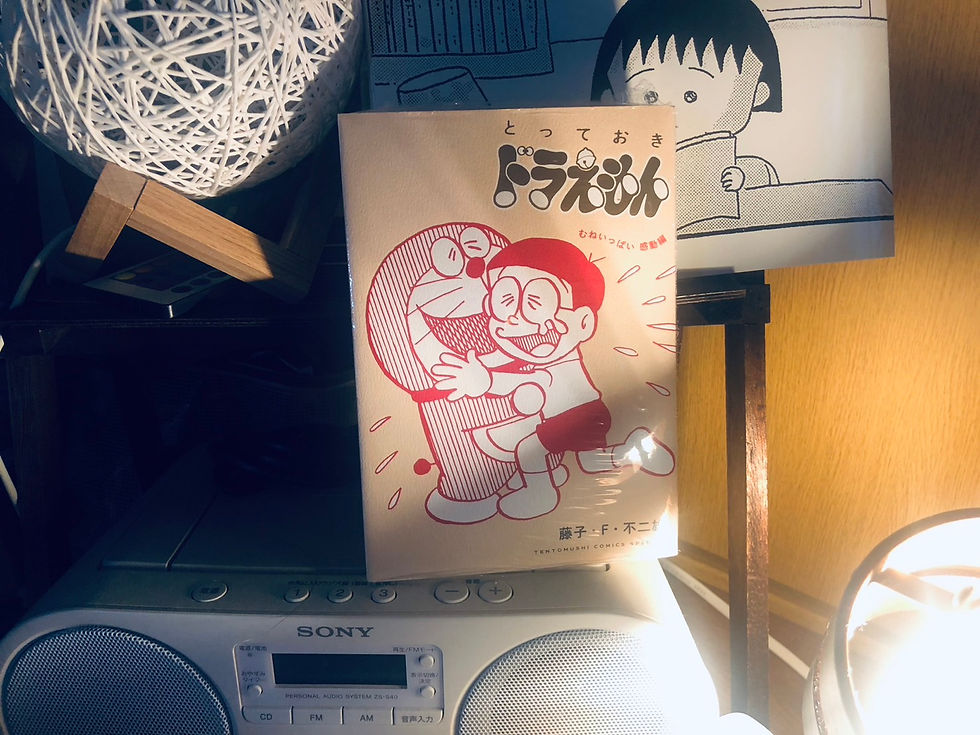
コメント